今日でリーべ運動あそびの6日間の研修が終わりました。
研修日最後は、滋賀県内にて3歳プログラムの実践指導を行いました。
実践指導の事後研修のなかで運動あそびで子どもたちがより楽しむためにはというテーマで振り返りを行いました。
その中で出てきた運動あそびはルールを守るからこそ、面白いということでした。
お山コーチ、島根のコブタコーチ、北海道のイクラコーチからの助言などを参考にルールを守るとはどういう事なのかを5つにまとめてみました。
ルールがあるからこそ面白い?
なぜルールを守るのかを伝える
どんなスポーツにも運動にもルールは存在します。それは運動あそびも同じです。あそびにこそルールは存在します。
ルールをみんなで守りながら面白さを追求するからこそ楽しむことができます。
サッカーはフィールドプレーヤーは手以外でしかボールをさわれないというルールがあるから面白い。
みんな手が使えるようになってしまえば競技は変わってしまいます。
ルールは最初から100%伝えるべきか?
ただ、幼児期の運動あそびに関してはやる前から100%ルールを子どもたちに伝えるべきかなのか?ということをコブタコーチから問われました。
ルールをしっかり守ってほしいという大人の気持ちからルールを伝え過ぎてしまうことがあるけどそれは本当に子どもたちのためになっているのか?ということ。
ルールの伝えすぎは大人の型にはめ込むだけ?
確かにルールはルールとして存在はしますが全て教えてしまうことで大人の型にはめ込んでしまう可能性が出てきます。
ルールを全て教えなくても子どもたち自ら考えて、コーチに質問をしてくるかもしれないですし、周りの状況をみてコーチの意図とした動きをしてくれるかもしれません。
どんな結果になるかはわかりませんがルールを伝えすぎないことで子どもたちの考えて動く力が可能性を見出すことが大切だと感じます。
ルールの教えすぎは発想力が高まらない?
ルールを教えすぎないことで子どもたちから意外な発想が生まれることがあります。
これはアフロコーチのブログで紹介されているエピソードなんですが動物に果物をあげにいくストーリーのときに果物をたくさん持っていこうとする友達がいました。
果物が今にも落ちそうな時、それをみた他の子が
「果物落としたら傷がついて美味しくなくなるよ」
と言ったのです。そうするとそう言われた子は
「そうか!」
と納得した様子で果物を1つづつ持っていくようになりました。
もし、コーチが最初から果物は1人一個だけというルールを決めていたらこの発想は子どもたちの中からうまれていなかったかもしれません。
もちろん、安全面に配慮した上でルールを伝えすぎないことが子どもの自由な発想を引き出すことにつながるんだと思います。
ルールを全て伝えなくても良い環境設定
また、環境設定のみでルールを伝えなくてよい状況を作り出すこともできます。
動物に果物を上げた後、子どもたちはきた道とは違う道を通ります。
そのときに写真のように次に果物を手に取るカゴをココにおけば自然と子どもたちはこの帰り道を通ってくれたかもしれません。
コブタコーチからのアドバイスは的確で「なるほど」と思いました。
ルールを全て伝えずにやらせてみる
聞くよりも見てみる。
見るよりも言ってみる。
言うよりもやってみる。
この言葉は大学の恩師の言葉。これをコーチにあてはめるなら、子どもに聞かせるよりも見させる。見させるよりも言わせてみる。言わせてみるよりもやらせてみる。
ルールは必要最低限だけ伝えまずはやらせてみる。子どもを信頼してみる。そうすることで大人が思いもしなかった発想力や想像力が発揮されるかもしれません。
子どもたちの能力は無限大です。その無限大の能力を引き出せるようにこれからも日々学んでいきたいと思います。
保育士研修会
運動あそびのルールづくりを学べる保育士研修会を行っています。
詳細はコチラからご覧になってくださいね^^

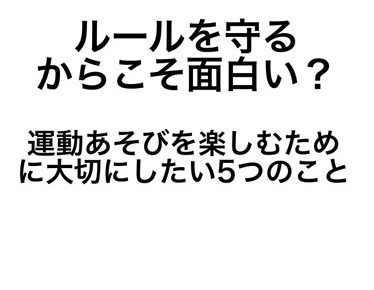
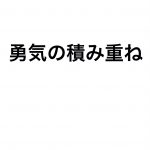
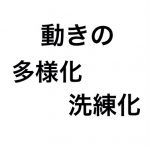

コメントを残す