この記事は親や保育者の話しかけによって赤ちゃんの脳はつくられる事を解説しています。
こんにちは!
いつも運動あそびで子ども達の笑顔で楽しさいっぱいのお茶コーチです。
待望の娘が生まれてもう早いものでもうすぐ3カ月。
ようやく視力が付いてきたのかモノや人の動きを目で追うようになってきました。
手の運動も活発になってきてモノをつかむことも増え、自分の服のヒモをよく引っ張っていつ間にか半分脱いでしまうまでに。毎回脱いでしまうのは困りものですが我が子の成長を微笑ましく感じています。
生まれて3ヶ月になる我が子ですが、子育てをしている親として(妻には到底足元にも及びませんが。。。)出来るのであれば良い環境で質の高い子育てをしたいと誰もが思うはず。
このブログを読んでいるあなたもその中の1人だと思います。
頭の良くなるおもちゃはないか探したり、今のうちから英才教育をしていくのが良いのではないかと考えたりする親御さんも少なからずいると思います。
私もその中の1人かもしれません。
でも、赤ちゃんにとって良い環境は頭の良くなるおもちゃでもなく、早い時期からの英才教育でもないことを私は尊敬する園長先生から教えて頂きました。
それは何か?
誰でも意識すれできる、とても簡単な事でした。高い教材を買わなくても、新しい勉強をしなくても誰もが毎日やっている事をちょっとだけ意識すればできてしまうことでした。
それは…
言葉です。
3歳までにおこる3000万語の格差
言葉?
とあなたは思ったかもしれません。
生活していく中で誰もが言葉を使います。耳に障がい者がある方でなければ言葉で伝えたり、伝えてもらったり。
誰かに何かを伝えるとき、考えごとをするとき、など言葉を使います。
言葉がなければ脳は発達していかない。海外ではこんな研究が行われています。
この研究では、異なる社会経済レベルに属する42家族の子どもを、生後約9ヶ月から3歳まで追跡観察しました。社会経済的なレベルは、家族の職業、母親の教育年数、両親の最終学歴、世帯年収(自己申告)で決められ、『社会経済レベルが高いグループ(専門職グループ)』に属する家族が13家族、『中度のグループ』が10、『低いグループ』が13、『生活保護グループ』が6となりました。
もっとも高い社会経済レベルの家庭に属する子どもたちが聞いた言葉は、1時間に平均2000語、一方、生活保護グループは約600語でした。
『黙りなさい』を子どもに3000万回言ってたら知的で実りの多い、安定したおとなに育たないと、誰でも直感的にわかるでしょう。
言葉の量が多い家庭には、量だけでなく、言葉の豊かさ、複雑さ、多様さといった要素も見られました。
3歳までにどれだけ言葉をかけてきたかで人生が決まってしまう。決して大げさなことではなく、三つ子の魂百までということわざがあるようにそれをこの著書の中で研究結果として紹介されています。
普段何気なく娘に言葉をかけていますがちょっと意識して言葉をかけて見たいと思います。
言葉は肯定的に
でも、言葉掛けといってもどんな言葉をかければいいのか?言葉であればどんなモノでもいいのか?
決してそうではないことも知りました。
「ダメ」「やめなさい!」のような否定的な言葉と「がんばったね」「うれしいね!」のような肯定的な言葉を使うのはどちらが良いか?
もちろん肯定的な言葉かけですよね。
「パパは〜ちゃんのことが大好きだよ」「ママは〜ちゃんが産まれてきてくれて幸せだよ」
と、多くの言葉をかけていくことが赤ちゃんの脳の育ちを促してくれます。
言葉の数よりも愛情
これまでに言葉の数や肯定的な言葉かけが大切といってきましたが、もっとも忘れてはいけないのが愛情です。
言葉の数は重要です。でも、まずは愛情に満ちた関係性が先で、それは赤ちゃんをケアする人がつくるものです。言葉の数はその次。言葉の数が多かったとしても、それが脳に良い効果をもたらすかどうかは、ケアする人が赤ちゃんにどう応答するかによりますし、ケアする人のあたたかさによります。
やはり、さいごは愛情。愛に勝る子育てはないということですね。
これからますます娘に愛情を注いでいこうと思えた素敵な本でした。
これから赤ちゃんを産む方、赤ちゃんが産まれたばかりの方にオススメの一冊です。
3000万語の格差 赤ちゃんの脳をつくる、親と保育者の話しかけ [ ダナ・サスキンド ]
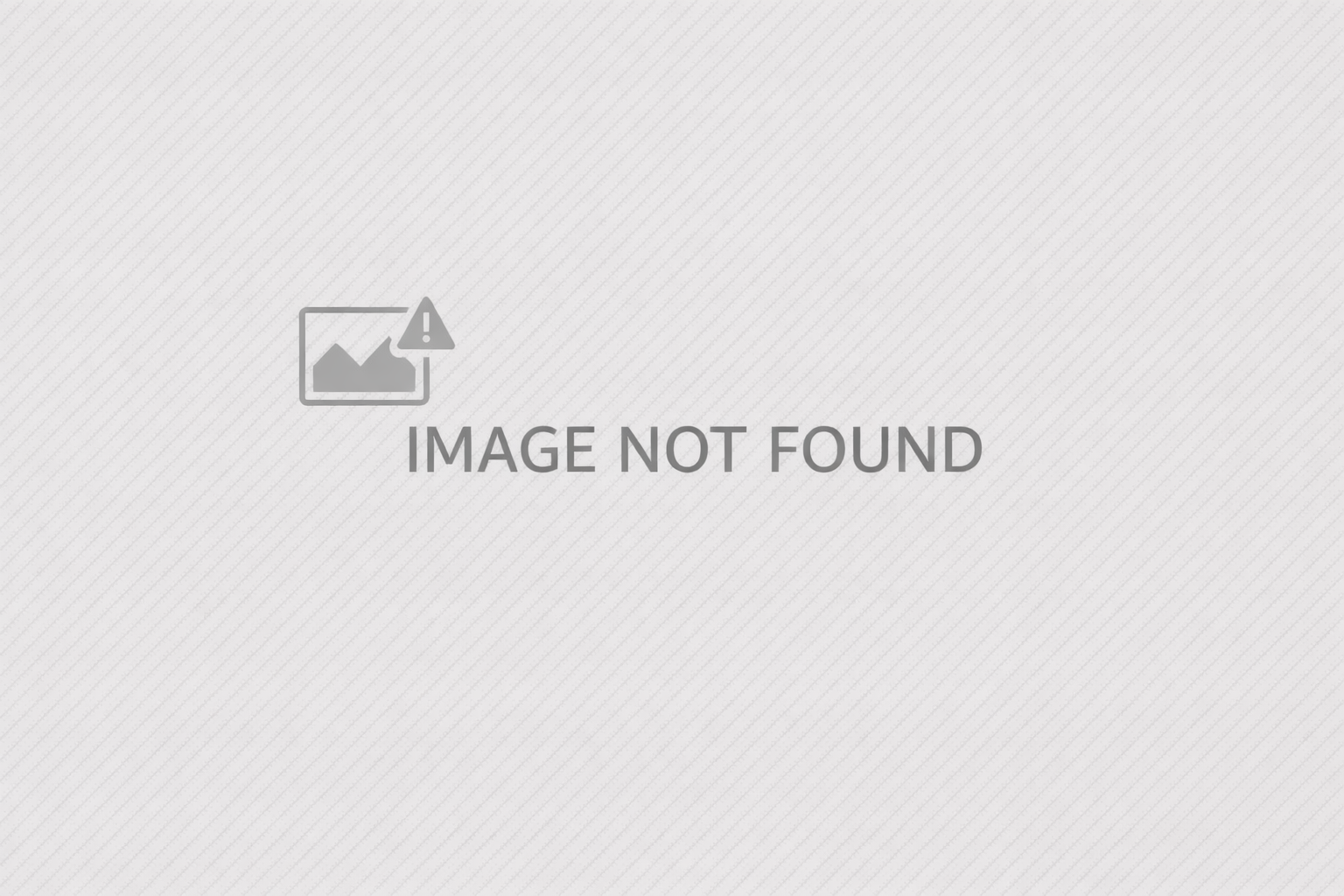


コメントを残す